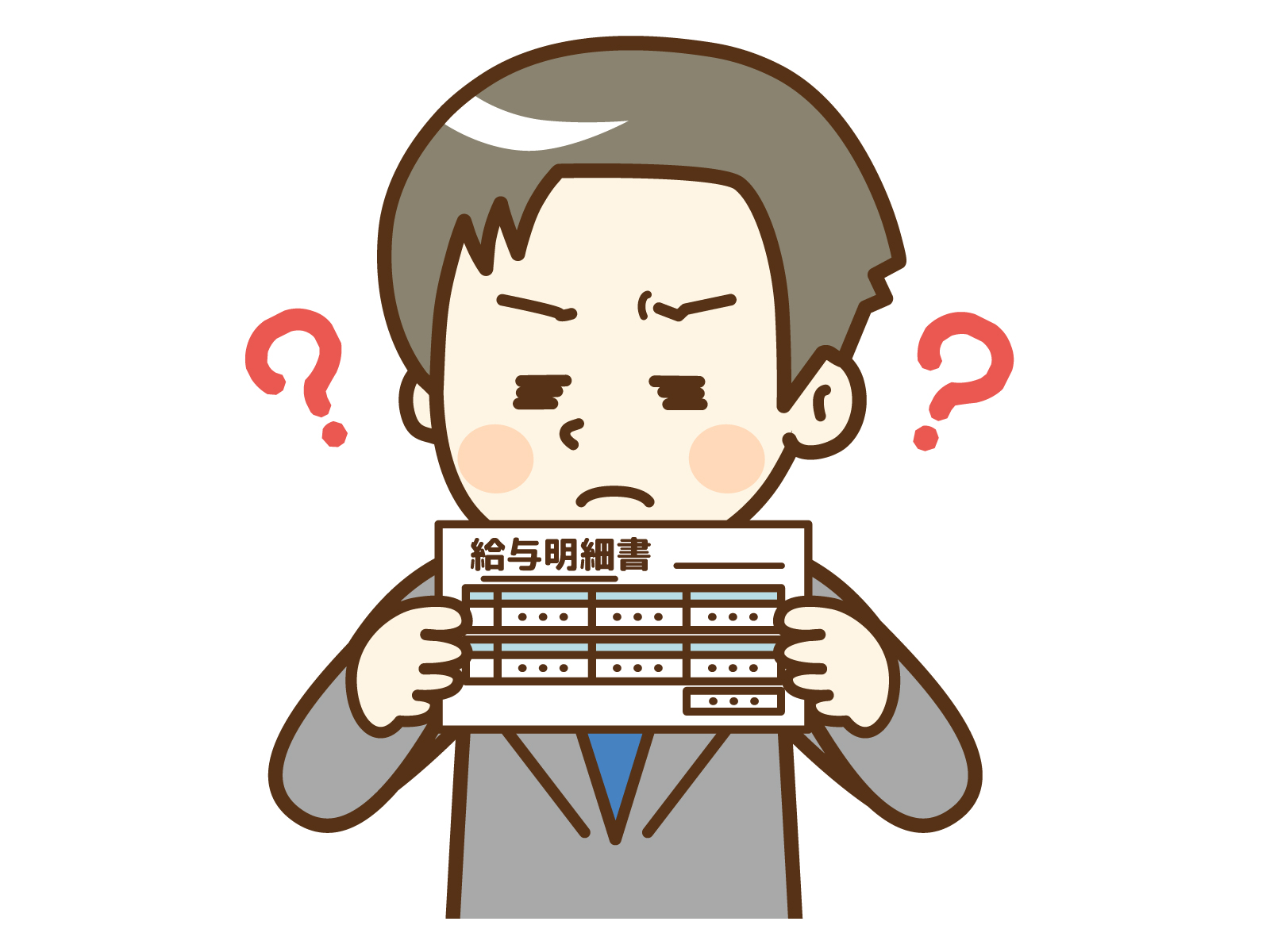📌 こんな方におすすめの記事です
- 障がい者雇用の定着率向上を目指したい人事担当者
- 多様な人材が活躍する組織文化を作りたい管理職・経営者
- 職場のコミュニケーションを活性化したいと考えている方
「障がい者雇用」と聞くと、何を思い浮かべるでしょうか。法定雇用率、助成金、配慮、特例子会社……。制度としての側面に焦点が当たることが多いこの分野ですが、実際に現場で支援や雇用に携わっていると、それだけでは語りきれない本音や温度感が見えてきます。
たとえば――
企業側の声
- 「障がい者って、国からお金がもらえるからお得なんですよね」
- 「軽作業なら任せられるし、コストも安く済むし」
- 「人手が足りないから、とりあえず1人入れてみようかと思って」
当事者側の声
- 「年金があるから働くのはリスクみたいに思えて」
- 「A型で働いてるけど、生活はギリギリ……もっと稼げたらいいのに」
こうした声が、特別珍しいわけではありません。どちらも、お金に対する不安や期待が根底にあります。すべてが悪意ある発言ではなく、制度への理解不足や、初期段階での誤解も含まれているのだとは思います。でもそのまま見過ごしてしまうと、「障がい者は安く雇えて都合がいい存在」というイメージだけが先行してしまい、本当に築くべき関係性からはどんどん遠ざかってしまうのです。
では、何が問題で、どこから整えていく必要があるのでしょうか。
お金の話は避けられない
支援や雇用の現場では、「お金」の話はどこか避けられがちです。助成金や給付金の存在があるとはいえ、実際にかかる費用、人件費の内訳、企業としての収支バランスなど、リアルなお金の流れについてはあまり語られないことが多い。
でも、本音で話をするなら、やっぱりお金の話は避けられません。
特例子会社や福祉的就労ではなく、一般企業が障がい者を雇用する場合、そこには当然「人件費」が発生します。そして多くの企業がまず懸念するのが「生産性」や「業務効率」とのバランスです。
「週20時間しか働けないなら、戦力としてカウントしづらい」 「指示やサポートに手間がかかると、周囲の負担が増える」 「正社員登用は難しいが、パートなら雇ってもよい」
こういった発想の根底には、「コストを抑える」という合理的な判断があります。もちろん、企業として健全な経営を目指すうえで、コスト感覚は欠かせません。ただ、それが「安いから雇う」という短絡的な理由になってしまうと、結果的にミスマッチや早期離職、職場内トラブルにつながってしまうのです。
助成金の役割を見直す
ここで少し制度の話をしましょう。
たとえば、精神・発達障害のある方を週20時間以上雇用した場合、企業は以下のような助成を受けられる可能性があります(※金額や条件は地域や制度改正によって変動あり)。
- 雇用調整助成金:年最大60万円(※1人あたり)
- 特定求職者雇用開発助成金:初年度最大240万円(※条件による)
- トライアル雇用奨励金:最大5万円/月 × 3ヶ月
- 精神障害者雇用特別奨励金:最大30万円(※条件あり)
これらを合算すると、1年間でおおよそ30万〜100万円程度の助成を受けられるケースもあります。仮に週20時間・時給1,000円の雇用で月8.6万円の人件費が発生したとすると、年間で約103万円。助成金を加味すれば、実質的な企業負担は大きく下がることになります。
…と、ここまで読むと「やっぱり安く雇えて得じゃないか」と思われるかもしれません。でも、助成金の本質はそこではありません。
助成金は、「安い報酬を補填するため」のお金ではなく、「職場として環境整備を進めるため」の資金なのです。つまり、合理的配慮の実施や業務マニュアルの整備、定着支援の体制づくりなど、雇用の“地盤”をつくるための準備資金。
そしてそれは、「今後、障がい者雇用が特別なものではなくなっていく時代に向けた備え」でもあります。
現在は助成金があっても、いずれ除籍金や制度自体が縮小されることも視野に入れておくべきです。その意味でも、今はむしろ「障がい者雇用を社内に整備する最大のチャンス」だと考えた方がよいのです。
“報酬”を設計し直す視点
ここで一度立ち止まって考えてみたいのは、「なぜ障がい者の報酬は低くなりがちなのか?」という根本的な問いです。
- 働ける時間が限られている
- 担える業務に制約がある
- スキルや経験の面で一般就労と差がある
たしかに、こういった要素は現実として存在します。でも、それは「だから安くていい」という話ではありません。
多くの職場で起きているのは、実はこうした事情に対する適切な評価と報酬の仕組みが「まだ整っていない」という状態です。つまり、「安く雇うしかない」のではなく、「どう評価して報いるかの設計がなされていない」という問題なのです。
本当に必要なのは、「生産性」だけで人を測るのではなく、その人が「どのような形でチームに貢献できるか」を丁寧に見つけ、その貢献に見合った報酬を支払える仕組みをつくること。
- 仕事の分解と再構築:業務を細分化し、それぞれの持ち味や得意なことに合う役割を丁寧に探します。単純な軽作業だけでなく、データ入力や書類整理など、集中力や正確性が活かせる仕事も多くあります。
- 個別の目標設定と評価:一律の評価基準ではなく、その人のペースや目標に合わせた評価制度を設計します。たとえば、作業の正確性、品質維持、チーム内の貢献度など、報酬につながる「評価軸」を複数設けることが重要です。
- チームとしての役割デザイン:本人だけでなく、周りの社員の役割も再定義します。誰が、どんなときに、どのようにサポートするのか。チーム全体で「違いを活かす」ための仕組みをつくることで、コミュニケーションが生まれ、協力体制が強化されます。
こうした取り組みを通じてこそ、「安いから雇う」の構造から抜け出し、一人ひとりがチームに不可欠な存在として認められる環境が生まれるのではないでしょうか。
雇うことで変わるのは、実は職場のほうかもしれない
最後に、ある企業の担当者が話してくれた言葉を紹介します。
「最初は、戦力になるかどうかばかり気にしていました。でも実際に雇ってみたら、思っていた以上に周囲の社員が変わったんです。業務の教え方、声かけの仕方、そもそも“働くって何だろう”という問い直しまで始まって…。むしろ私たちが育てられた感じです」
障がい者雇用は、たしかに簡単ではありません。制度も複雑で、実務も一筋縄ではいかないことばかりです。しかし、「義務だから」「安いから」という短絡的な視点から一歩踏み出すとき、そこにはコスト削減以上の価値が待っています。
障がい者雇用は、企業の価値観や文化を問い直し、すべての社員にとって「よりよい働き方」を考えるきっかけとなる、強力な原動力です。多様な人材がそれぞれの持ち場で活躍する職場は、創造性や問題解決能力が高まるだけでなく、社員一人ひとりが「自分らしく働ける」という安心感にもつながります。
報酬の本質を問い直すこと。それは、障がいのある人たちを「安く雇える存在」として見るのではなく、ともに未来を築く「大切な仲間」として受け入れること。それこそが、企業と働く人、そして社会全体に持続的な豊かさをもたらす第一歩になるはずです。
サイドストーリー(当事者の気持ち)はnoteにて投稿しています
「障害者雇用枠で正社員になったのに、こんなはずじゃなかった」
──昇給も昇格もない職場で、当事者たちが抱える”静かな絶望”
障がい者雇用を通じた組織づくりについて、お困りごとやご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。ともに、すべての社員が自分らしく輝ける職場を作っていきましょう。